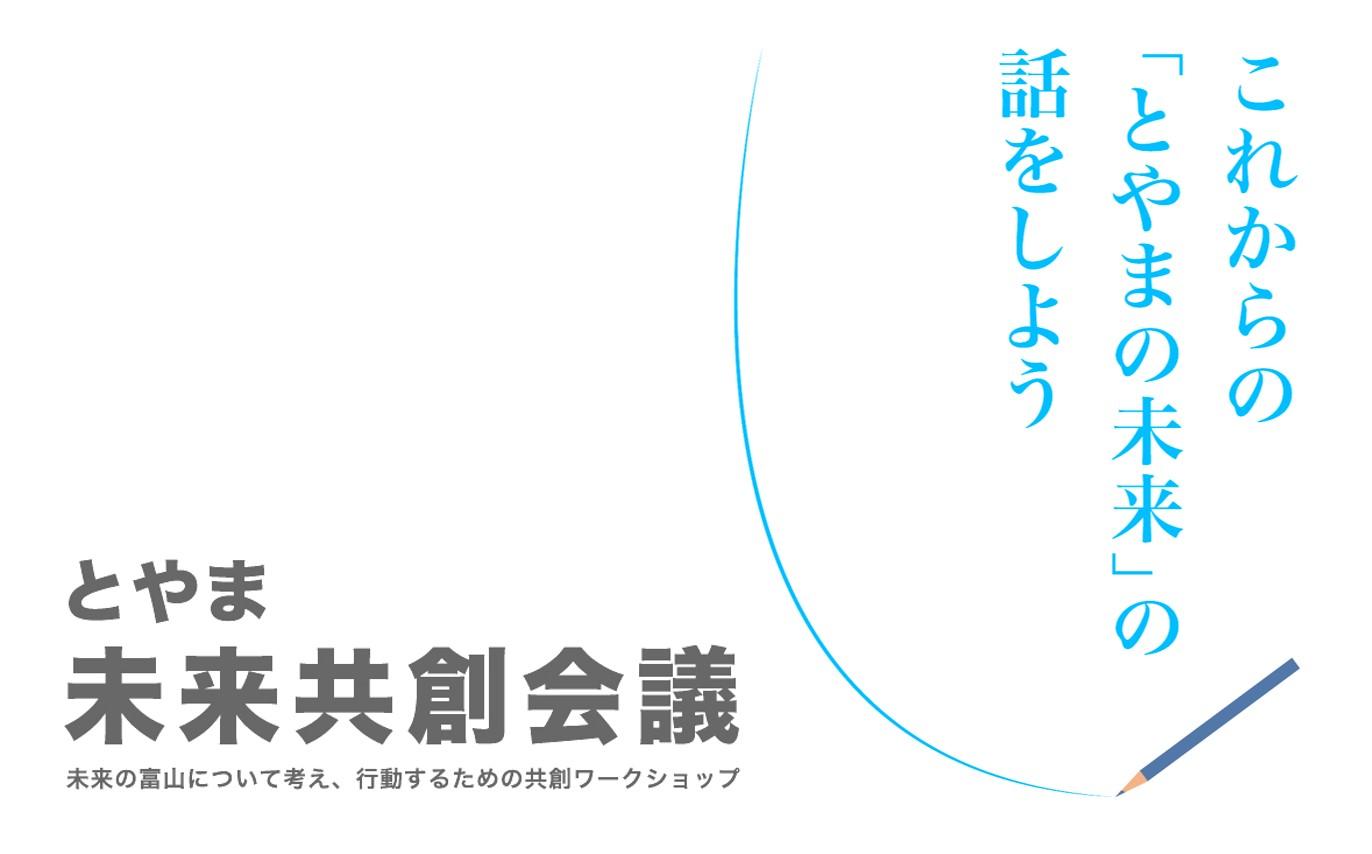Day1:気候変動の現状と将来、実施できる取り組みを考える
2025年9月27日(土)、スケッチラボにて「地域に根差した魅力あるゼロカーボン」を考える第1回ワークショップを開催しました。本ワークショップは、2050年のゼロカーボンシティ実現に向け、市民一人ひとりが「豊かさ」を感じられる未来の暮らしを具体的に描き、その実現に向けたアイデアを共創していくことを目的とし、全4回の開催を予定しています。
第1回は「気候変動の現状と将来、実施できる取り組みを考える」をテーマに、専門家からの情報提供と、それらを踏まえたグループ対話を行いました。
プログラムレビュー
まず、茨城大学の三村先生より、「気候変動の現状と未来 ~ゼロカーボンシティの実現に向けて~」と題してご講演いただきました。

世界全体の気候変動の傾向が示された後、猛暑や豪雨といった形で私たちの生活にどのような影響を及ぼすのかが概説されました。そのうえで、「気候変動対策は、環境のためだけではなく、都市の新たな魅力創出や市民のQOL(生活の質)向上につなげる『新しい都市開発の機会』として捉えられる」という重要な視点をご提供いただきました。例としてデンマークのコペンハーゲン市が紹介され、平常時は公園として利用しつつ大雨の際には水を貯める遊水スペースや、新たな地場産業として栄える風力発電など、気候変動対策がまちの魅力や産業につながっている事例が共有され、参加者のみなさまも非常に関心を持って活発な質疑応答になりました。
続いて、地球環境戦略研究機関(IGES)の渡部研究員より、「私たちのくらしと温室効果ガス」をテーマに、より身近な視点からの情報提供がありました。

渡部研究員からは、「大前提として排出量を減らす必要はあるものの、私たちのくらしからの温室効果ガス排出は、住んでいる地域性や家庭・個人の状況・志向によって大きく異なる」というお話をいただきました。例えば、富山市の郊外に住む人が移動をすべて公共交通機関に切り替えたり、肉好きな人が明日から完全な菜食主義になったりするのは、なかなか現実的ではありません。
「自分や自分の家庭にとって何であれば取り組みやすいか、そしてそれをより継続しやすくするためにはどうしたらよいか」を考えることが重要、という点は、今後の議論においても活かされることでしょう。
講義で得た知見ももとにしながら、2050年の富山における豊かなくらしを考えるグループ対話を実施しました。対話では、「富山の持つ価値や未来に残したいものは何か、それを活用しながらどのような脱炭素が実現できるか」という視点で、活発な意見交換が行われました。

出されたアイデアの一部をご紹介します。
・豊かな山や海といった自然資源や伝統文化を次世代に残し、楽しむ生活をしたい。特に、富山の伝統工芸である能作のグラスで美味しい地ビールを飲みたい。
・2050年には日本全体のDX・GXが進み、グリーンかつスマートな都市が前提となる中で、富山の豊かな自然資源の存在が大きな価値になるのではないか。「ネイチャーシティ」を前面に押し出すことで、富山に住みたい人が増えるのでは。
・豊かな緑を活かした農園併設型のキャンプ場を作り、週末は家族でレジャーを楽しみたい。子ども向けの体験農園や食育プログラムを展開することもできそう。
・富山の名産品である昆布の養殖を推進し、CO2を吸収するブルーカーボンの創出と、食や交易の歴史文化の伝承を同時に進めることで、地域文化の保全と脱炭素を両立できるのではないか。
次回に向けて
今回のワークショップでは、参加者の皆さんの対話を通じて、2050年の豊かなくらしの断片が少しずつ見えてきました。
次回以降のワークショップでは、今回生まれたアイデアの種をヒントにしながら、より具体的な未来のライフスタイル像を描いていきます。
「富山の価値を維持しながら、それと同時に脱炭素も実現する」という考え方のもとで、地域住民と協働で、地域の価値や残したいものが何なのかを考えてみましょう!

 LINE
LINE
 Twitter
Twitter
 Instagram
Instagram
 facebook
facebook